 神道・神仏習合
神道・神仏習合 『諸神本懐集』9 園城寺(三井寺)の新羅明神
初めての方は『諸神本懐集』1からどうぞ 『諸神本懐集』8のつづき 園城寺(三井寺)の新羅明神 かの新羅の明神ときこゆるは、園城寺の鎮守なり。 園城寺(おんじょうじ・滋賀県大津市)は天台寺門宗の総本山で御本尊は弥勒菩薩。 通称は、三井寺(みい...
 神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合 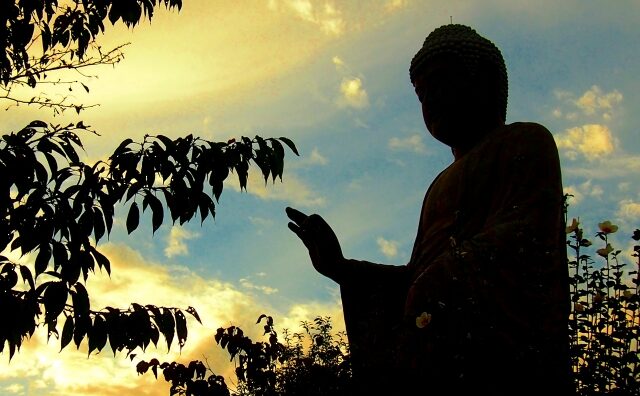 神道・神仏習合
神道・神仏習合 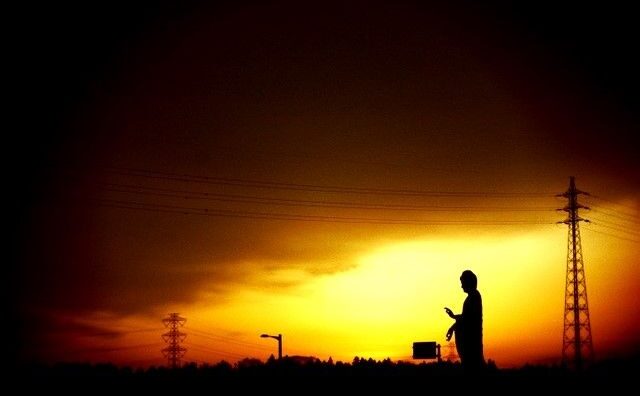 神道・神仏習合
神道・神仏習合  神仏
神仏  神仏
神仏  大和葛城宝山記
大和葛城宝山記  大和葛城宝山記
大和葛城宝山記  大和葛城宝山記
大和葛城宝山記  神仏
神仏  神仏
神仏  大和葛城宝山記
大和葛城宝山記  神道・神仏習合
神道・神仏習合  先代旧事本紀
先代旧事本紀  先代旧事本紀
先代旧事本紀