 仏教・瞑想
仏教・瞑想 『無畏三蔵禅要』1 善無畏三蔵 一行禅師 敬賢和上 慧警禅師
善無畏三蔵(637-735)は、真言密教における伝持の第五祖であり、『大日経』を唐に伝え、弟子の一行禅師らと共に漢訳しました。 『無畏三蔵禅要』は、善無畏三蔵が、嵩山(すうざん)会善寺の敬賢(660-723)に、戒と禅定について説かれた教え...
 仏教・瞑想
仏教・瞑想  真言宗
真言宗  大和葛城宝山記
大和葛城宝山記  中臣祓訓解
中臣祓訓解  仏教・瞑想
仏教・瞑想  チベットの瞑想法
チベットの瞑想法 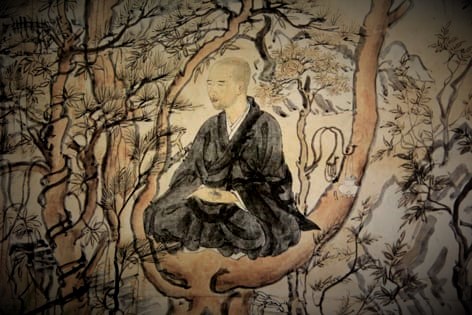 仏教・瞑想
仏教・瞑想 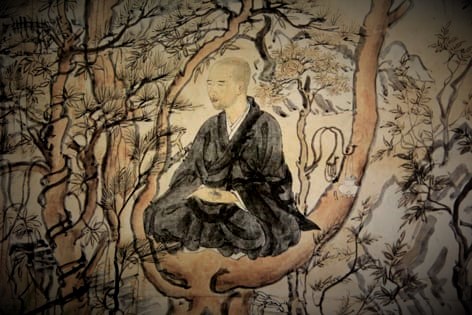 仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想 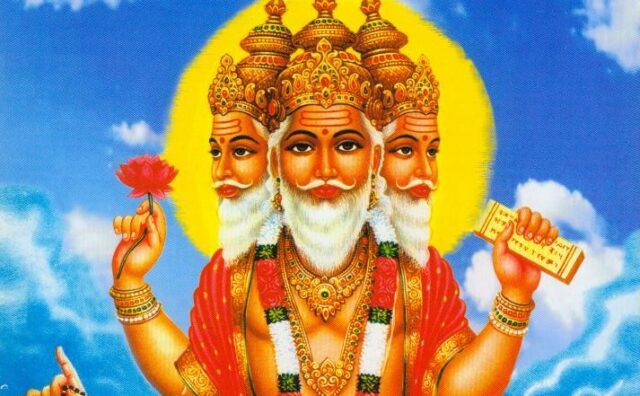 仏教・瞑想
仏教・瞑想 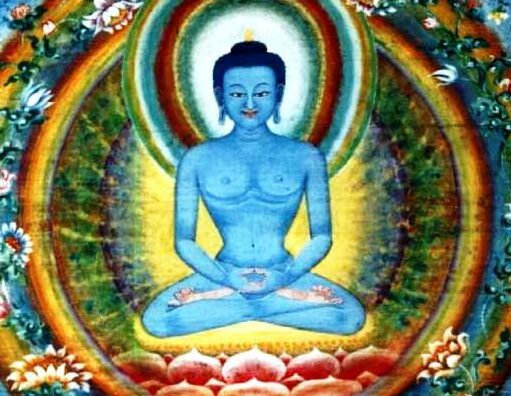 仏教・瞑想
仏教・瞑想  真言宗
真言宗 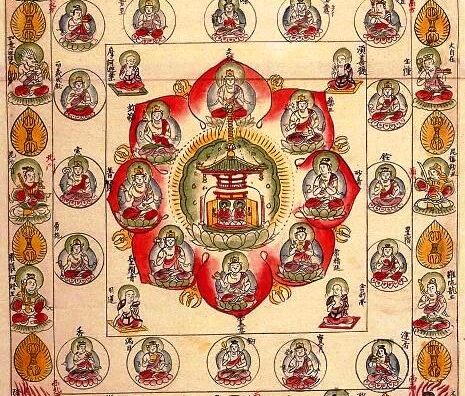 仏教・瞑想
仏教・瞑想