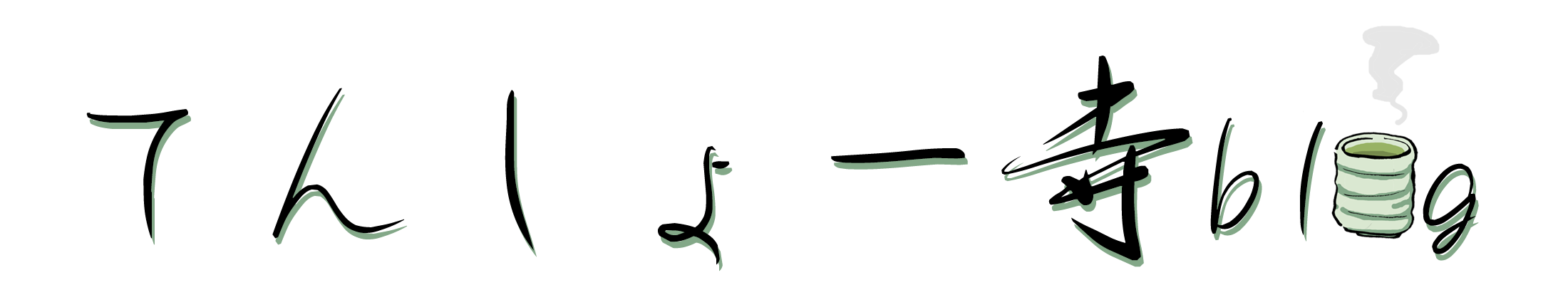日が暮れた後、私はバスに乗り込んだ。
エアコンバスは日本の観光バスそのままだった。
ミヤンマーの車は、日本から輸入した中古車がほとんどだが、塗装し直さないので車体に観光会社の名前がそのまま日本語で書かれている。
私は一番前の補助席に、威圧的に「座れ」と言われた。
補助席の背もたれははなかった。
次のバスに乗れるかと尋ねると「ノー」と凄まれた。
バスが闇の中へと走り出した。
エアコンバスの窓は開かないようになっている。
エアコンを使うことが前提で設計されているからだ。
エアコンは使われなかった。
車内はミヤンマー人たちの腋臭でむせかえっている。
振り向くと斜め後ろに座っている白人が露骨に顔をしかめていた。
外国人は、私とその白人だけだった。
白人がたまりかねたように怒鳴った。
「エアコンをつけろ!」
乗務員は、すまし顔で言った。
「エアコンは故障中」
「これはエアコンバスじゃない!差額を払い戻せ」
乗務員は、ガラスがはずれてる運転席の窓を指さした。
「これがエアコンだ」
バスは砂利道に入った。車内が、がくがく揺れ始めた。
背もたれのない補助席で私は前後左右に揺られた。
隣の男が、細かく痙攣する手で、くわえたばこに火を付けようとしている。
バスの揺れに加えて、手の痙攣とも奮闘していたが、しばらくして火を付けることに成功した。
男は満足気にふーっと煙をはきだした。
煙は、隣に座っている私の顔を覆った後、白人の席まで流れていった。
白人は勢いよく身を乗り出してきた。
白人と隣の男とを結ぶ線上に私が座っていたので、白人は私にのしかかる格好となった。
「これが見えないのか!」
白人は社内に貼ってあった禁煙マークを指さした。
隣の男はきょとんとした顔で、白人の顔を見ていた。
「火を消せ」
男は英語が理解できなかった。
バスが停まった。
私は前の補助席に座っていたので、乗降の邪魔だと言われバスから降ろされた。
外は本当の闇だった。
街灯一つなかった。
大半の乗客が降りたが、バスの灯りが届く範囲からは誰も離れなかった。
パンクだった。
バスのタイヤはすべてすり減っており、溝がなくなっていた。
これではパンクしないほうがおかしい。
白人は、すべてのタイヤを取り替えることをしきりに訴えたが、誰も聞く耳を持たなかった。
白人は首をかしげながら、横にいた私に同意を求めた。
虫たちがバスの灯りにぞくぞくと集まってきた。
「どこから来た?」
白人は私に尋ねた。
私が日本人だとわかると、笑いながら私の肩を強く叩き、
「昔、一緒に戦ったな!」と言った。
彼はドイツ人だった。
もちろん私たちが一緒に戦ったわけではなく、ドイツ人は大東亜戦争のことを言っているのだった。
ドイツ人はミヤンマー人のマナーについて非難を始めた。
私は黙って聞いていた。
乗務員が何か叫んだ。
乗客がバスに乗り始めた。
タイヤ交換が終わったのだ。
バスが走り出す。
乗客の大半が喫煙を始めた。
バスの中はすぐに煙で満たされていた。
ドイツ人は、もう何も言わなかった。
私は煙にむせながら、背もたれのない座席で揺られていた。
ドイツ人は私に同情した。
「席をかわってやるよ」
私は遠慮せずに席をかわった。
車内が振動する。
ドイツ人も振動する。
揺れは、次第に激しさを増してゆく。
揺さ振られるドイツ人の顔は、妙におもしろかったので私はしばらく笑い続けた。
ドイツ人が叫んだ。
「ギブアップ!」
またドイツ人と席をかわった。
今度は、私が揺さ振られた。
ドイツ人は大笑いしていた。
バスはいくらも走らないうちに再び停まった。
私は再び、邪魔だと言われ、バスから降ろされた。
シャツがすっかりたばこ臭くなっていた。
虫たちがバスの灯りにぞくぞくと集まってくる。
また、パンクだった。
ドイツ人は、再びミヤンマー人を非難し始めた。
私は再び、黙って聞いていた。
乗務員は慣れた手つきでタイヤをはずした。
パンク修理は、この国のバスの乗務員にとって、日常的な仕事の一つなのだろう。
ガラスを強く叩く音がした。
窓を見上げると、巨大な蛾が窓ガラスに身体を打ちつけていた。
繰り返し、車内から射す光に向かって、頭から突っ込んでいく。
繰り返し身体をぶつけ、繰り返しガラスにはじかれている。
ドイツ人はまだ非難し続けていた。
バスは再び走り出すだろうが、またパンクを繰り返すだろう。
蛾は繰り返し、身体を打ちつけている。
幾度も繰り返すうち、羽が少しやぶけ、鱗粉が散った。
幾度も無意味な行動を繰り返し、自らを傷つけている。
暗黒の闇の中で、始まりさえない遠い過去から、すべての生き物が同じことを繰り返している。