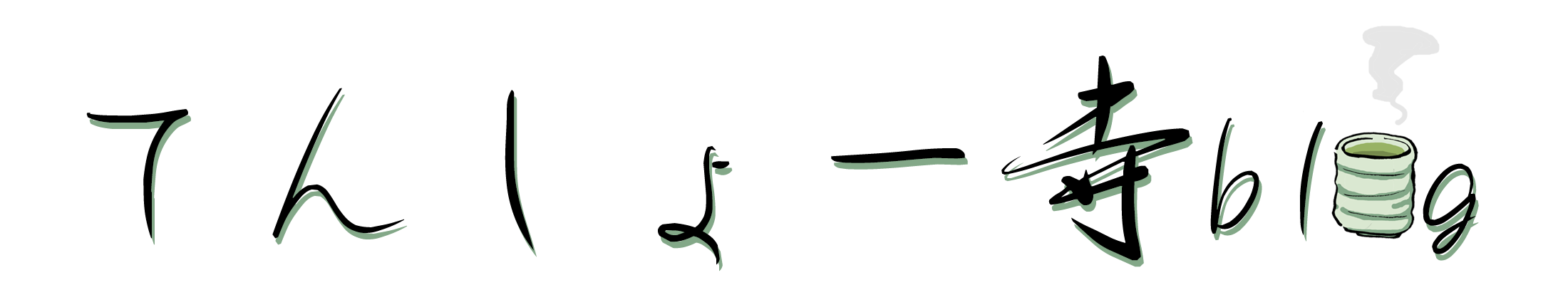綿アメをうすーく引きのばしてみたような軽い雲が浮いている。
よーく見ていると、ゆっくりと形を変えながら、少しずつ西へ流れていくのがわかる。
水色の大空の下は見渡す限りの広大な平原だった。
赤茶けた大地のところどころには木や茂みが生えていたが、それらと同じくらい仏塔が地平線近くにまでまばらに続いていた。
すべての仏塔が、みごとに風景に溶け込んでいる。
一口に仏塔と言っても、そこには様々な形がある。中には黄金に輝いているものさえあるのに、それらはまったく作為を感じさせなかった。
仏塔はまるで人の手を借りずに、大地からタケノコのように生えてきたかのように、まったく自然だった。
幻想的な風景の中で、私は馬車に乗っていた。
馬は、馬主の言うことをちっとも聞かなかった。
右に曲がろうとしているのに、左にばかり曲がって行く。
「馬が、こっちに行きたいと言ってるもので……」
馬主は、人の良い困った表情でそう言うばかりだった。
インドでも馬車に乗ったことがある。
ラージギールの馬車馬は、言うことを聞いても聞かなくても、常にこっぴどく叩かれていた。
馬はそのたびに悲鳴をあげ、私はそのたびに悲しくなった。
帰り道は歩いて帰った。
それ以来、インドでは馬車に乗ってない。
この馬主が馬を叩かないことは良いことだ。
馬主は、馬のためにたびたび休憩し、ペットボトルから水を飲ませ、草をはませた。
急いではいけない。
この調子では、今日、行こうと思っていた仏塔すべてには行けないかも知れない。
しかし、急がないスピードが人間が生きていく本来のスピードなのだ。
このスピードに慣れると人は穏やかになれる。
馬は本当にわがままで、言うことをほとんど聞かなかったが、馬主を心から信頼しているようだった。
馬主に甘えてみたり、すねたりしてみせた。
馬主は、その度に困ったような、それでいて、とてもうれしそうな顔をした。
目を見開いていられないほどの強烈な夕日の中、私たちは一つの仏塔の上に登った。
眼下に広がる大地に、太陽が沈んでゆくのをそこで待った。
強烈な日の光が世界を真っ赤な光と真っ黒い影にくっきりと引き裂いていく。
林立する仏塔の黒い影が、真っ赤な大地に目に見えて伸びてゆく。
それは、まったく現実離れした圧倒的な光景だった。
強烈な光の中で、私はまったく無意識のうちに合掌し、頭を下げていた。
一切の存在が圧倒的なまでに尊く、美しかった。