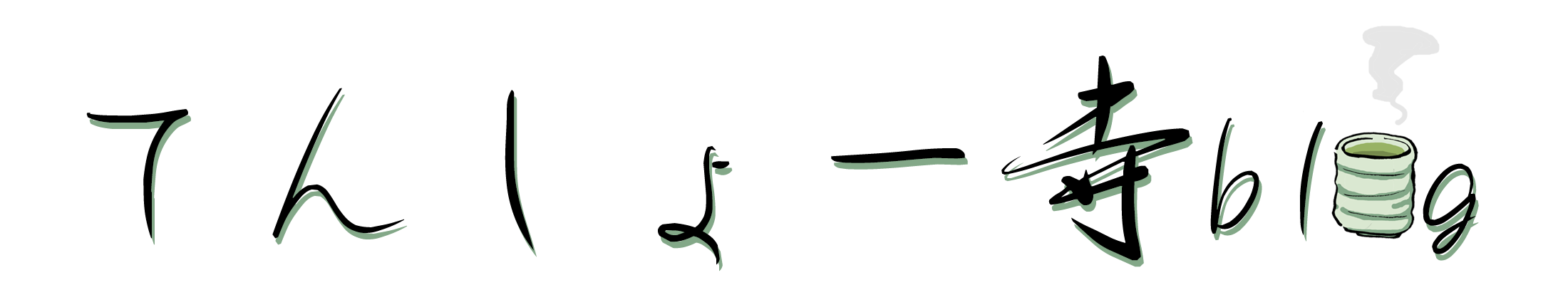ミヤンマー北部にチェントンという外国人に対しては非解放となっていた小さな町がある。
チェントン出身の友人から何度も「チェントンはいいところだから一緒に行こう」と誘われていたのだが、私はチェントンに行くことにずっと躊躇していた。実際に言った人たちはみんな口を揃えて、「これといって見るものがない」と言っていたからだ。
タチレクというタイと国境を接した町からタクシーをチャーターして舗装してない道を揺られていく。
タチレク以外からは空路でしか入域が許可されていない。
何度か検問で止められながら、砂煙を巻きあげるタクシーに揺られて5時間、ようやく到着した。
見るものが何もないはずのこの小さな田舎町で、私は生涯、忘れられないであろう光景を目にしてしまった。
次の日の早朝、友人が宿まで迎えに来てくれた。
シミのついた汗臭い枕と、耳元でうなる蚊の羽音、蒸し暑さのせいでほとんど眠れなかった。
夜間は、ほとんどの時間が停電で、天井からぶら下がった扇風機がまわりだしたのは暑さがやわらいできた明け方近くになってからだった。
私たちは、それぞれ別々のバイクタクシーの後部座席に乗った。
二台のバイクは追い越したり、追い抜かされたりしたが、その度に友人は笑いながら「後ろから手を離せ」といった。
チェントンでは、座席の後部を後ろ手に握って乗るのはすごく格好が悪いのだそうだ。
チェントンは、小さな町というよりは大きな村という雰囲気だ。
友人たちの話によれば、この村はミヤンマー軍に占領されているのだという。
自分たちはタイヤイ人でミヤンマー人ではないといい、言葉もタイ語の方言だ。
この地域は数百年前から、ミヤンマーとタイが取りあっていた地域で独立した国ではなかった。
だから国際的には、まったく注目されていないのだが、住民たちはミヤンマーの圧政に苦しんでいるという。
市場の前でバイクが止まった。
市場はかなり大きく、商品によって区画が決められていた。
中国産のコピー商品が並ぶ雑貨の区画で両替した。
遠くで「ルーク、ルーク(子ども、子ども)」と年寄りが大声が聞こえた。
何だかすごく嫌な気がした。
その声が今にも泣きだしそうな悲しみに満ちたものだったからだ。
友人が「行こう」と私の肩をたたいて走り出した。
魚屋の前の少し広い場所に黒い民族服の年寄りが何人か座っている。
もうすでに人だかりができていた。
黒い服の年寄りたちも、集まっている人たちも、みんな一様に悲しい顔をしている。
山岳民族のお婆さんが、背負ってきたのであろう編み籠の中では赤ん坊が泣いていた。
黒い服の年寄りたちは、自分たちのかわいい孫を売るために遠い山の向こうから歩いてきたのだという。
お婆さんは見ているだけで泣けてくるほどに悲しい顔をしていた。
赤ん坊の値段は日本円に換算すると、たった五千円くらいだった。
山岳民族が住んでいる山はミヤンマーの領土だが、そこに住んでいる人たちはミヤンマー人とは認められていない。
そのため、どんなに困っていても国の援助は何も受けられないし、外国人が立ち入ることのできない地域なので、諸外国にはその悲惨さが知られていない。
私は、買ったばかりのもち米が入った袋と五千円ほどのミヤンマー紙幣をお婆さんに渡すと、すぐに後ろを向いて立ち去ろうとした。
いたたまれなかったのだ。
この世界はたくさんの矛盾を抱えている。
世界には、まだまだ知られていない悲惨な現実がある。
後ろで、お婆さんが声を絞り出すように何か言っていたが、よく聞こえなかった。