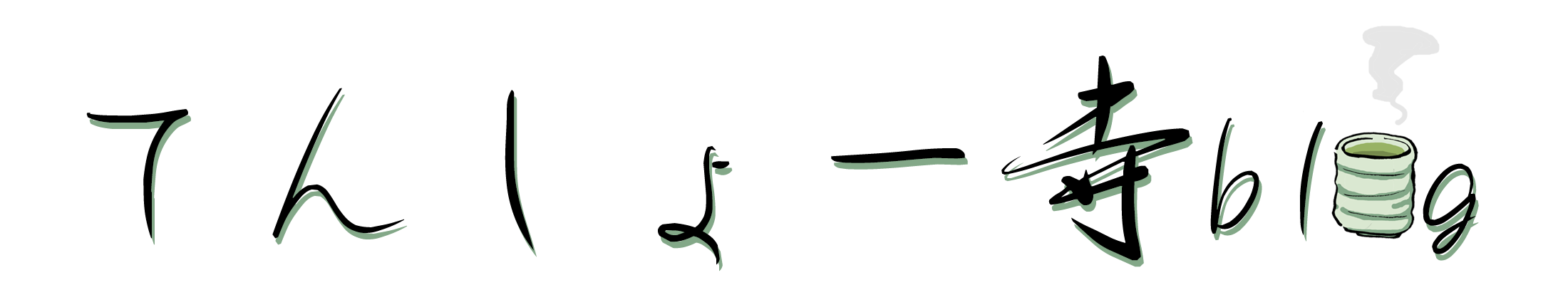その日は、谷底に祀られている女神に、生け贄が捧げられる日だった。
神の前にいる聖職者は、実に手際よく、生け贄をさばいていく。
施主から鶏を受け取ると同時に、頭をひねり首をねじ切る。頭を祠の上に投げ置き、胴体から噴き出す血を神像にかける。
胴体を施主に手渡すと、すぐに次の鶏を受け取る。
十畳ほどの白いタイル張りの床に、赤い血が染みわたってゆく。
おびえる子山羊が、首に紐をくくられ引きずられてきた。
鶏が殺されてゆく横で、山羊は床に押さえつけられ、鉈で首を叩き落とされた。
私は座って、動物たちが殺されていく空間を観つづけた。
この殺されていく個々の生き物は、永遠に限りなく近い時間、悠久の過去から繰り返してきた無数の転生のどこかで、自分の母だったことがあったのだ。
始まりのない遠い過去から、私たちは数え切れない回数、生まれ変わってきた。
その無限に近い転生の中で、目の前の生き物が一度は私の母になったことがあるはずなのだ。
殺されてゆく母を見て、悲れみを生じない者などいるだろうか。
床は全面、鮮やかな色に血塗られた。祠の上には、鶏の頭が何百個も積まれていた。
鶏の屠殺場を、影像で見せられたことがある。
生きたまま逆さづりにされ、熱い水蒸気が満ちた箱に入れられ、毛をむしられていた。
ベルトコンベアーに乗った鶏たちは、事務的に処理され、単なる材料として扱われていた。
そこには、命の尊厳などなかった。生命は、無視され、存在していないかのように扱われていた。鶏がいくら泣き叫んでも、誰も相手にしなかった。
屠殺場で働いていた人と話したことがある。
「生き物を扱っているとは、思わないようにしている。そうでなければ、やっていけない」
屠殺場の鶏たちの死は無視され、意識的に死の意味を無化されている。
水場では、女神からのお下がりである鶏の胴体を洗う人たちで満ちていた。
皆どこか、うれしそうだった。今夜は御馳走なのだ。
生け贄に捧げられた動物たちは、天界に転生するのだという。
機械的に捌かれた鶏と、神に捧げられた鶏の「死」に、違いはあるだろうか。
少なくとも、女神に捧げられた「死」は、意味を持たせられていた。
私は生け贄を批判する気はない。
生け贄をやめても肉を食べる以上、どこかで何かが殺されるからだ。
だから、屠殺場を批判する気もない。
しかし、肯定する気にもなれない。
この相対的な世界には、絶対的な価値は存在しえない。
父親に手を引かれ、寺院から出ていく幼い男の子は、もう一方の手に、切り落とされた山羊の頭をぶら下げていた。
山羊は絶望と悲しみに満ちたうつろな目で、ゆらゆらと揺れながら私を見ている。
私は、生け贄を批判する気はない。
ただ、殺されていく生き物たちが、殺されていく母たちが可哀想なだけだ。