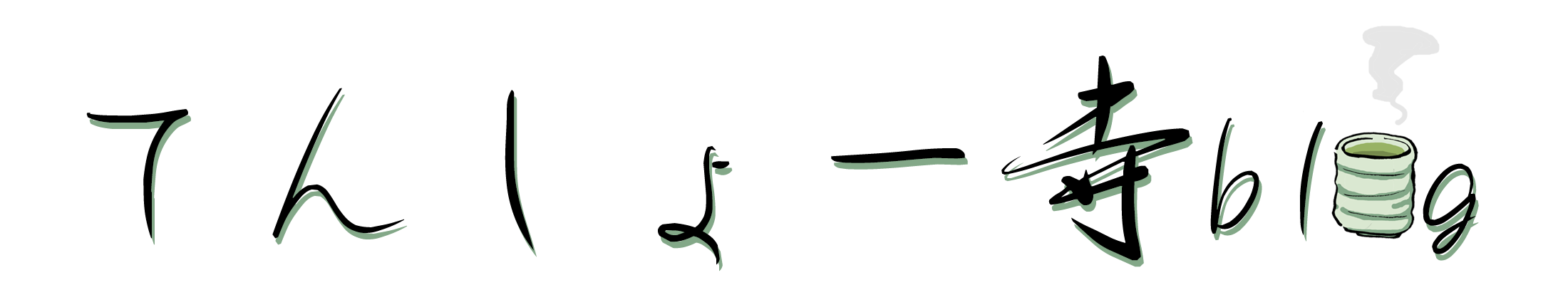朝食の後、宿から一歩外に出ると、宿の前でたむろしていたサイカー乗りたちに囲まれた。
インドのリクシャーは客席が自転車の後ろに付いていたが、ミヤンマーのサイカーは客席が自転車の横に付いている。「サイドカー」なのだろうが、ミヤンマーでは「サイカー」と呼ばれている。
私は歩いた。
五人の男が、私についてきた。
男たちは、サイカーに乗るようにしつこくすすめていたが、宿から遠く離れていくにしたがって、一人ずつ離れていった。
橋までついてきたのは、インド人だけだった。
「俺の顔がこんなだから、おまえはサイカー乗らないのだろう」
私はインド人に対して、まだ一言も発していなかったが、インド人は自分が悪人面だということをひどく気にしていた。
「インド人にだっていい奴がいるんだ。ルックスはインド人でも、俺の心はミヤンマー人だ」
私は、インド人だから悪い人だとも、ミヤンマー人だから良い人とも思っていなかった。どこの民族にも、良い人も悪い人もいるものだ。
インド人は、折り目が切れかかった茶色く変色したノートの切れ端や、海外から送られてきた手紙を差し出した。
ノートや手紙には、彼の仕事振りと人柄を讃歎する言葉が並べられていた。
その半分くらいは、日本人が書いたものだった。
「初めは悪い人かと思ったけど……」、「疑ってごめんなさい」などと書かれていた。
インド人は、鬼のような形相で怒鳴った。
「家には年老いた母と、病気の妻と、四人の子供たちが、俺の稼ぎを待っているんだっ!」
自転車の横にちょこんと取り付けられた小さな椅子に、私は座った。
インド人は、今にも泣きそうな顔で「ありがとう、ありがとう」と私の左手を両手で握った。
そこまで喜ばれるとは思ってもみなかった。
私はシュエモード・パゴタに行くように頼んだ。
シュエモード・パゴタはビルマ三大仏塔の一つで釈迦如来の遺髪が祀られている。
インド人は「あそこは夜の方がきれいだ」と言って走り出した。
案の定、他の所に連れて行かれた。
インド人は一日中必死だった。
私は一日中、振り回された。
もう疲れたので、次は仏塔に行くように言っても、「あそこは夜だ」と言って、興味のないところに連れて行かれた。
「興味深いだろう?」と何度も聞かれ、少しだけと何度も答えた。
太陽が西に沈み、街を照らすものが暗い街灯だけになったころ、サイカーはやっと仏塔に向かって走り出した。
インド人は元気だったが、私はすっかり疲れ果てていた。
大通りに出ると、巨大な仏塔がライトアップされ、暗い街に浮かび上がっていた。
道はまっすぐ仏塔に伸びている。
ぐんぐんと、インド人がペダルを踏み込むたびに、ぐんぐんと仏塔が大きくなっていく。
近づけば、近づくほど、それは巨大だった。
そして、かなり近づいたその時、突然、仏塔が消え失せた。
仏塔を中心とする視界のすべてが、劇的に消え失せたのだ。
一瞬、失明したのかと思った。が、目が慣れてくると、夜空の星がこんなに多かったのかと気付かされた。
停電だった。
町中の灯りも、仏塔を照らしていたライトも、人工的な光はすべて消え失せていた。
闇に溶け込んだ見えない仏塔に向かって、何事もなかったかのように汗だくでペダルを踏み続けているインド人の険しい顔がぼんやりと見えた。