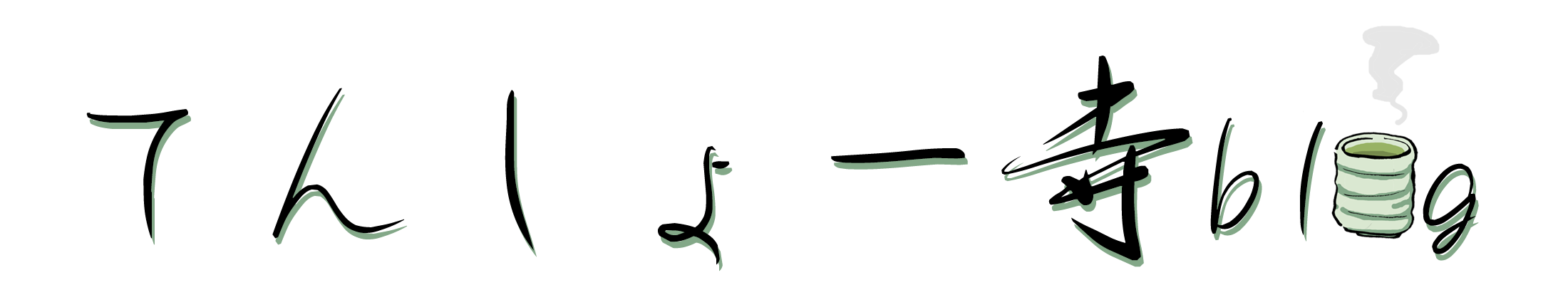数ヶ月かけて南インドとスリランカを一周した後、私は再びヴァラナシへ戻ってきた。
牛と人とゴミだらけの町。
ところどころ牛糞が放置されている路地を宿へ向かう。
宿のオヤジは私の顔を見ると目を見開いて見せた。
「元気?ネパールはどうだった?」
今回はネパールじゃないよ。南へ行くって言ってたじゃないか。
「そうそう、南へ行ってきたんだろう。知ってるよ」
忘れてただろう。
「ハハハ、何でもいいよ」
荷物を預けるとすぐにガンガーへ向かった。もつれあった細い路地を走る。途中何度も人とぶつかりそうになる。
祠の横にうずくまっていた男が機敏に立ち上がるのが見えた。
男は躍り出るように私の前に立ちはだかった。
「まだ、ここにいたのか」
いつかの男だった。彼の口臭には覚えがあった。
瞳孔が開きっぱなしで黄色く濁った眼球を持つ男は、この街では珍しくない。
しかし、この臭いを持つのは彼しかいない。
変わってないな。
「いや、変わってしまったよ。ワタシも、あんたも。変わってないものなんか無いよ」
私は返事をせずに走り出した。
背後で男が何か言ったが、聞き取れなかった。
もつれあった細長い路地を一本一本走り抜けていく。
路地が途切れた。
世界が一気に明るくなり、視界が広がった。
眼下には雄大な女神が流れていた。
シヴァの髪から流れ出したガンジス河だ。
茶色く濁っていて、それでいて淀んでいない。
ゆったりとした流れは同時に、底なしの深さを感じさせる。
広大な河の向こう側は霞んで見えた。
此岸には人間のために岸をコンクリートで階段状に固めたガートや建築物、人や牛やゴミなどが密集している。
しかし、彼岸には人工的なものは何もなかった。
ぼんやりと砂と草の色が見えるだけだ。
たまにボート漕ぎに向こう岸まで連れて行かれた旅行者が行方不明になるらしい。
此岸には火葬場がいくつかある。少し川下にあるのが一番大きく、その上には火葬を眺める場所まである。
遺族たちは柵にもたれ込み、眼下にある火葬場をのぞき込んでいた。
年寄り達の後ろから、私は二ヶ月ぶりに燃える屍を観察した。
仏教の修行者は釈迦如来の時代から、死体を観て無常を瞑想してきた。
死から目をそらせてはいけない。
死体を包み込んでいた白い布が燃えると、中に隠されていた死が露出する。
火にあぶられた遺体が「く」の字に起きあがる。
火葬場で働く者は容赦なくその乾燥した体をへし折り火の中にくべる。
もう人間扱いはされない。
もう人間ではないから。
ヒンドゥー教には、一般人の遺体や遺骨を崇拝する文化はない。
かつて人間だったものは、意識と分離することにより人間の形をした人間ではないものとなった。
一切が炎の中に投じられたとき、肩を振るわせていた老婆がよろけ、隣の女性の肩に泣き崩れた。
横顔が見えたのは一瞬だった。
その横顔は、数ヶ月前のいつか、路地裏で息子らしき男を彼にけしかけた老婆に見えた。
本当にそのときの老婆なのか確認しなかったし、する気もなかった。
どちらにしても、それは同じことだからだ。
死者の灰は川へ流された。
生まれたものは死ぬ。
集められたものは離散する。
輪廻世界に存在するもの、それらは何一つとして同じであり続けるものは無い。
人の希望とか欲求にはまったく関わり無く、すべてはそれぞれの業により流れてゆく。