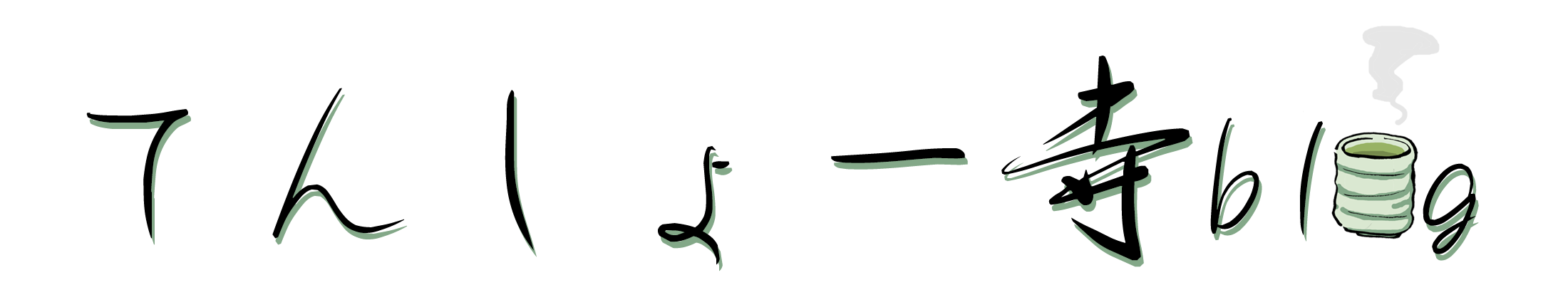祠の横に座っていた男と目があった。瞳孔が開きっぱなしの黄ばんだ眼球。
男は立ち上がった。
妙に痩せているのは覚醒剤かヘロインか。
男がひょこひょこと歩いてきた。ここの住民の大半は不健康に見える。
男は小汚い顔を容赦なく近づけた。男の顔が近すぎて視界がぼやけた。
男が今、肉眼で外界を見ていないのはあきらかだ。
男は妙にこなれた日本語と、ヤニと唾液と得体の知れないものが混ざって発酵したような臭いを発した。
「バラナシ来たの初めて?ガンジャ?チャラース?」
男はしつこかった。路地を曲がり早足で歩く私を、執拗に追いながら早口でまくしたてる。
路地を曲がる。
男は執拗に追ってくる。
インドは必死だ。
生きるのに必死なのだ。
日本人のように必死さを隠す術を知らないから、欲望を剥き出しでぶつかってくる。
金を得るためには、見え透いた嘘だってつく。暴力だってふるう。
幸せそうな人は圧倒的に少ない。闘争心を剥き出しに、自己の利益を主張する。
このがむしゃらさが逆のベクトルを向いたとき、極端な修行者があらわれる。
インドは良くも悪くも極端だ。
路地を曲がる。
男は黙ってくるりと向きを変えた。
長い警棒を持った警官が何人かでチャイをすすっていたのだ。
男はそそくさと左手の路地へ入った。
警官たちは、鋭い目つきで私を睨みつけている。
私は足早に路地を右へ曲がった。
私は、はっとして立ち止まった。
壁に描かれていたシヴァ神に目を奪われたのだ。
それは幼児のいたずら描きのような本当に稚拙な絵だった。
しかし、その絵は何度も繰り返し供養され、ティカという赤い粉やオレンジ色の花びらなどが絵の上から何重にも擦り込まれていた。
赤い粉をまぶされたその神は、血しぶきを浴びながら無邪気に笑う子供のようだ。
何とも不気味な気迫に満ちている。
この絵を供養する人たちの真剣な力が、この絵に神を宿らせたのだ。
仏画は単なる絵ではない。
仏像は単なる彫像ではない。
絵や彫刻の善し悪しに目を奪われていたら本質を見失う。
われわれは画や像を礼拝しているのではなく、画や像の向こう側にある相対性を越えた真実を拝しているのだから。