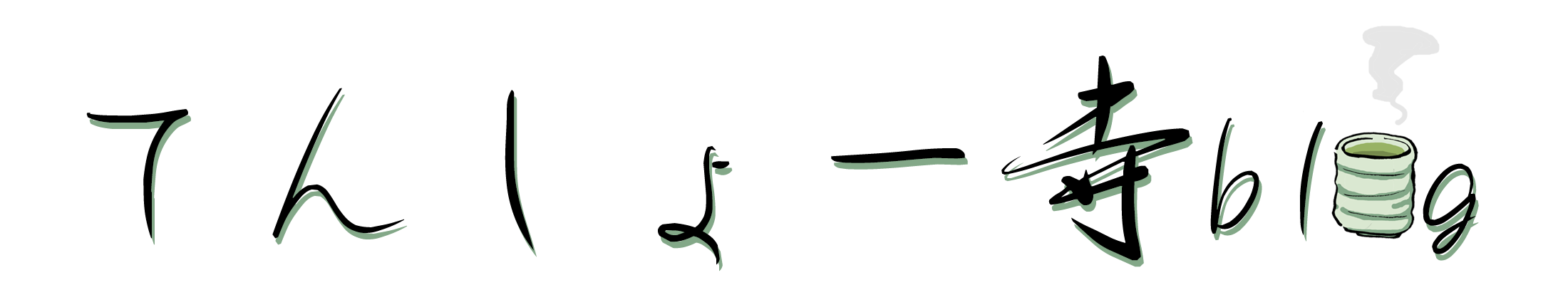ウブドは芸術の村である。
「ジャングルに行けば、いつでも果物があり、河に行けば、いつでも魚がいるから、食べ物のためにあくせく働く必要がなかった。村中みんなが、暇つぶしに絵を描いたりしていたんだよ」
雨宿りのために偶然、入り込んだ画廊の主人は話し好きな人だった。
「村中のみんなが絵を描いたり、彫刻をしたりしていたから、欧米人が島に入ってくる前は、アートが金になるなんて、誰も考えていなかったんだ」
そのことは四十代の主人が生まれる以前の話であるが、主人は実際、その時代を生き抜いてきた老人のようにそのことを話した。
主人は、コーヒーカップに口を付けようとして、はたと気付いたように、私のカップにお湯を注いでくれた。
「どうぞ」
バリコーヒーの粉は、お湯に溶けにくいので、何度もお湯をつぎ足しながら飲んでゆく。
何杯目かのお湯を注がれたあと、私は画廊を後にした。
太陽が沈み、雨はあがっていた。
夜道を歩いていく。あらゆる方向から虫の鳴き声が聞こえる。
画廊の主人に勧められたカフェの看板が見えた。
カフェの敷地内には大きな蓮池があった。というより、大きな蓮池のほとりにカフェがあるという塩梅だ。
夜の闇の中で、赤い照明により照らし出された蓮池は不気味だった。
池にせりだした席に座り、蓮池を眺める。
この光景は、私が抱いていた極楽の心象風景ではないか。
極楽は阿弥陀如来の浄土である。日本では阿弥陀如来の皮膚の色を金色で表現することが多いが、チベットでは赤色であるし、真言密教にも紅頗梨色阿弥陀如来として赤色の阿弥陀如来が伝えられている。阿弥陀如来は報身仏であり、報身仏は精妙な光の次元の仏である。つまり赤い光は阿弥陀のメタファーとなっている。阿弥陀如来は蓮華部の仏であるから赤い光に照らされた蓮池は極楽浄土を連想させるのだ。
極楽は文字通り、すばらしい場所にちがいない。ところが、いつも死のイメージが同居している。
幼少の頃、祖父が仏壇を新調した。新しい大きな仏壇は黒光りして異様な存在感を放っていたが、私には扉を開いて中を見せてはくれなかった。どうしても仏壇の中を見たい私は一人で仏間に忍び込み、新調したばかりの仏壇の扉をおそるおそる開き、中をのぞき見た。
漆黒の仏壇の中は金箔でキラキラに輝いていた。そこには金ピカの阿弥陀如来とご先祖様の位牌が安置されていた。見てはならないこの世ならぬ光景に幼い私は魅せられた。
しばらく見入っていると背後に気配を感じた。振り向くと遠い親戚の婆さんが私を睨みつけていた。
あの時、祖父がなぜ仏壇の扉を開いてくれなかったのか、親戚の婆さんがなぜ私を睨みつけていたのか、二人が亡くなった今となっては確かめようがない。
二人は今、極楽浄土にいるのだろうかなどと考えつつ、私はコーヒーをすすった。