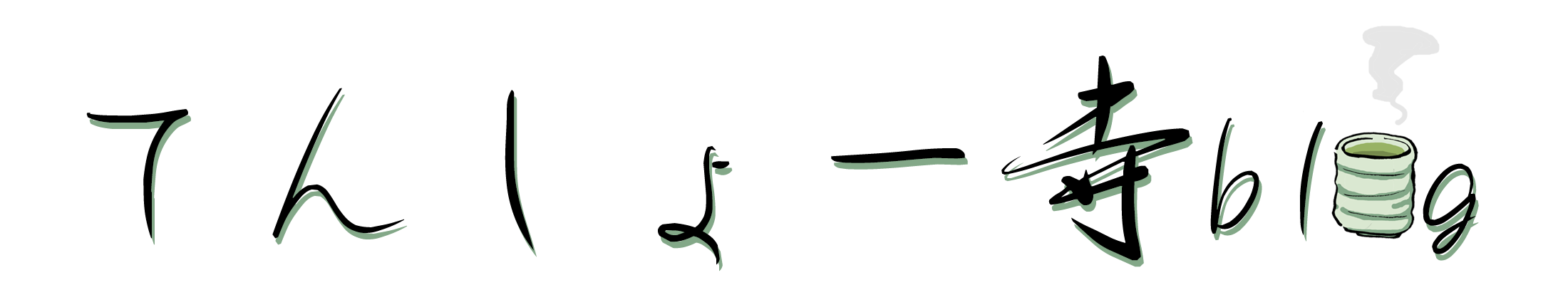あたたかい遠浅の海は、どこまで歩いて行っても、ひざより深くならず、やわらかい藻が足にからみついた。
「だから、人が来ないんだよ」
バンガローを経営しているおばさんが、砂浜から言った。
人が来なくて波の音がしない海は、瞑想修行に良い。
パンガン島はヒッピーの島として有名だが、ヒッピーは波が高く、パーティーが行われる東のビーチに集まる。
浅く波が無く、泳ぐことができない西の宿には、ゆっくり読書するような年配の欧米人しか来なかった。
「ここは何も無いけど、ゆっくりするにはいい所だよ」
椰子の木が茂る海沿いの敷地内に、二メートル四方の小さなバンガローが、十個くらい点在していた。
私は、この小さなバンガローでリトリートすることにした。
部屋は隙間だらけでいつも蚊が飛び回っていたが、風通しが悪く暑かった。
日が暮れると、小さな暗い電球が一つあるだけなので、字が読めなくなった。
毎晩、薄闇の中で波の音を聞くことなく聞き、夢の中へ入っていった。
朝日が昇ると、私は、念珠と経典を持って、小さな砂浜に座った。
椰子の木陰で一日中、観想の海に浸った。太陽は、刻一刻と位置を変え、気が付くと私の肌を焼いていた。
一座終えるごとに、私は、動きまわる木陰の中へ移動しなければならなかった。
太陽が真上に昇ったころ、私は立ち上がり、母屋へ歩いていく。
おばさんは、面倒臭そうにチャーハンを炒めながら、振り向かずに言った。
「チャーハンね」
おばさんはなぜだか、私の昼食はいつもチャーハンである、と決めていた。
低温で炒められたチャーハンは、いつものように油ぎっていた。
砂浜に歩いて行く。
鮮やかな蜜柑色のイグアナが、私のために素早く場所を空けた。
砂浜から眺める海は、どこまでも深い青だった。
太陽の日差しを受け、小さな波がきらきらと輝いていた。
太陽が傾き、椰子が木陰をつくらなくなった頃、私は、いつしか、独りになっていた。
小さな砂浜に、椰子と、青い海と、赤い太陽と共に、私は、独りであった。
そこは、場所全体の中心であった。
一人でいることが、独りであることなのではない。
大衆の中にあって独りであることは、まったく可能なのだ。
ひとかけらの思考も無く、観察しているものも、観察されているものも無く、ただ、独りになったとき、ある神聖さが世界を内蔵していることを知る。
太陽が残していった色彩が色褪せてゆき、月の輪郭がはっきりしてくるまで、私は砂の上に座っていた。