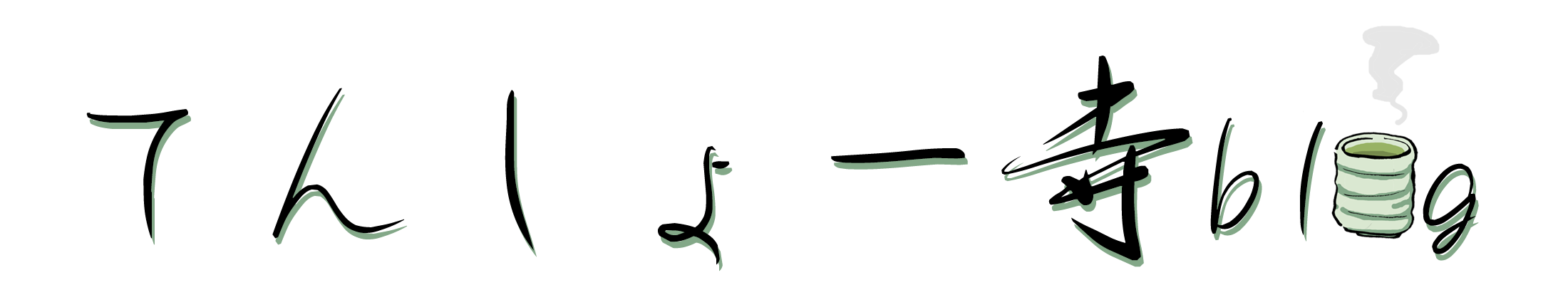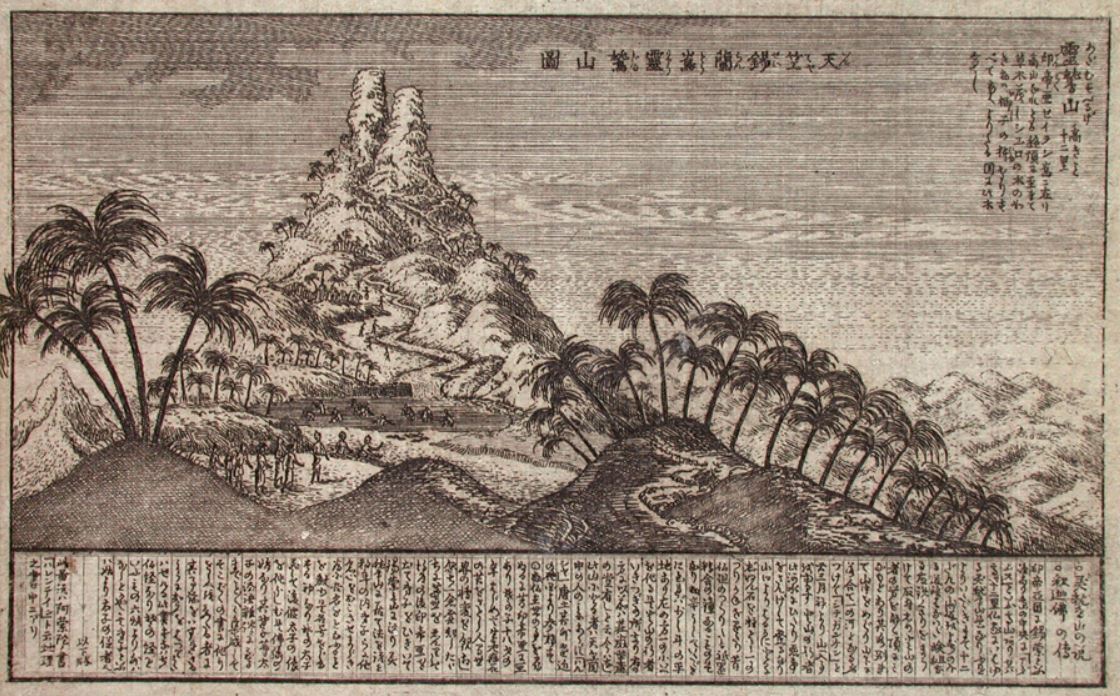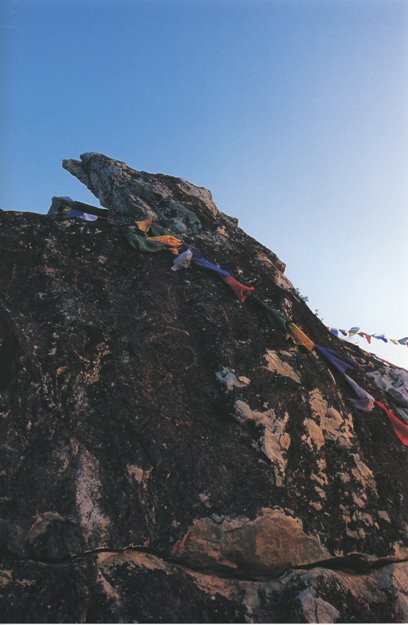ラージギールは仏典に出てくる王舎城だ。カビくさい安宿のベッドに荷物を置くと外に出た。
この町は埃っぽかった。
認識されるもの、すべてが埃をかぶっていた。
十字路の角のチャイ屋の前で、プラスチックの椅子に座った。
老人は何も言わず、しかめ面のまま人差し指を立てて見せた。
私はうなずいた。
ひん曲がったアルミ鍋から、コップに注がれる甘いチャイ。
熱いコップをのぞき込むとミルクが膜を張っていた。
夕暮れのこの町は、幼い頃に見た輪郭がはっきりしない夢の中の光景に似ている。
あまり健康的ではない人の心象風景のようだ。
どんよりとした紅い空の手前に、砂煙を上げる牛の群れがあらわれた。
坂の上から数百頭が下りてくる。
リクシャーが路地に逃れていく。
人と犬と鶏たちが道の脇へ寄った。
「椅子をひっこめろ」
あわてた老人がしかっめつらで私に言った。
牛はヒンドゥー教徒たちにとって聖なる生き物だ。うるんだ眼球が好奇心旺盛にぐりんぐりんと世界を見まわしている。
牛は、一旦飲み込んだ物を口中に戻して、噛み直してから再び飲み込む「反芻」という習性がある。
目の前の半数の牛たちが、泡った胃液を口からあふれさせ、口を動かしている。
聖なるものは必ずしも「善」、あるいは「浄」であるとは言えない。
究極の真実は「善」と「悪」、「浄」と「不浄」、あらゆる二元論を超越しているからだ。
「善」も「悪」も「浄」も「不浄」も、すべてはその中に飲み込まれている。
道いっぱいにひろがる牛の流れは、あらゆるものを無差別に飲み込んでいく。
飲み込まれた馬車が立ち往生している。馬車乗りは無表情に牛を眺めている。
二匹の犬が牛たちの足の間で戸惑っている。その仕草がなんともいえず可愛らしい。
子犬と母犬。
母犬は道に飛び出した。縫うように牛たちの足の間をすり抜けて行く。子犬も後を追う。
子犬の歩幅は狭く、せわしなく四本の足と尻尾を動かしている。
牛の歩みにタイミングを合わせ、飛び込まなくてはならない。
母犬は慣れたもので、すいすいと泳ぐように彼岸へ渡りきった。
母犬は振り返り子犬を探した。
ゆっくりだが確実に大地を踏みしめる何百本もの牛の足。
タイミングがずれた。
子犬は持ち上げた牛の右足に押され道の上で横になった。
母犬が見ている。
右足はちょうど子犬の腹に降ろされた。
ゆっくりだが確実にふみしめられていく。
やわらかな子犬の腹を。
母犬はただ見ていた。
いくつもの蹄が、瀕死の子犬を跨いでいく。
去りゆく牛の背はどれも似ている。
どの牛が子犬を踏んだのかは、もう、わからない。
それらが一つの波になって何事もなかったかのように去っていく。
事実、牛たちにとっては、何事もなかったのだろう。
馬車が動き出した。路地からはリクシャーが入ってくる。
子犬は、口から泡だった血をはきだしたまま、激しく呼吸していた。
母犬は近寄ったまま立ちつくしていた。
周りを見回して助けを求めているかのようだった。
その仕草は人のようだった。
母の行動だった。
母は子のために助けを求めていたが、誰も近寄ろうとしなかった。
私も近寄らなかった。
もう誰の目にも、子が死ぬことは明白だったからだ。
鮮やかな血の色が視覚野に焼き付いた。
手に持っていたコップを覗くと、冷えたチャイの表面にはミルクの膜が張っていた。
膜は、私の手の揺れにあわせて、ぶよぶよと揺れている。
途方に暮れている母子に、馬車が道を塞がれた。馬車乗りが鐘を鳴らす。
母は馬車乗りを見上げた。
馬車はもう一度、鐘を鳴らした。
母犬は子犬をくわえ道の脇へ運んでいった。
私はまぶたを強く抑えた。
立ち上がり、老人にコインを渡すと、老人は首をかしげて見せた。インドでは、肯定のときは首を縦に振らず、首をかしげるのだ。
星が少ない空に奇妙なほどシャープな月が出ている。
横たわった子犬と、それを見守る母犬の姿。母の顔はもう暗い影になっていたが、母の表情がどういうものか、見なくてもわかった。
宿の扉を開くとカビの臭いが鼻腔をついた。
頭陀袋を放り投げ、靴を脱ぎ散らかしたまま、ベッドの上で蓮華座を組んだ。
口の中で経文を唱えて、目を閉じた。
視覚野に可愛らしい母子を映し出す。
牛の流れ。
流れに乗る母と、流れに逆らう子。
踏みつぶされる子。
それを見る母。
繰り返し、母子が悲しみ、繰り返し、哀れみで満たされていく。
涙が首を伝い流れて、上着に染み込んでいく。
繰り返し、子の腹ががつぶれ、繰り返し、母が嘆く。
それが何度繰り返されたのか、いつのまにかわからなくなっていた。
時間が消え去っていた。
そこは、哀れみだった。
ただ、哀れみだった。
哀れみそのものである無量の哀れみ。
そこには、赤くつぶれる子も、嘆く母も、牛たちも、瞑想する私も、誰もいなかった。
そこには、哀れむものも、哀れられるものもいなかった。
ただ、哀れみだった。
法華経が小説のように読めます。 全品現代語訳 法華経 (角川ソフィア文庫)