 神道・神仏習合
神道・神仏習合 『諸神本懐集』15 宝応声菩薩=観音菩薩、宝吉祥菩薩=勢至菩薩
初めての方は『諸神本懐集』1からどうぞ『諸神本懐集』14のつづきこの二菩薩、ともにあひはかりて、第七の梵天にむかひ、その七宝をとりて、この界に来至、日月星辰、二十八宿をつくりて、天下をてらし、春秋冬夏をさだむ。ときに、ふたりの菩薩あひかたり...
 神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合 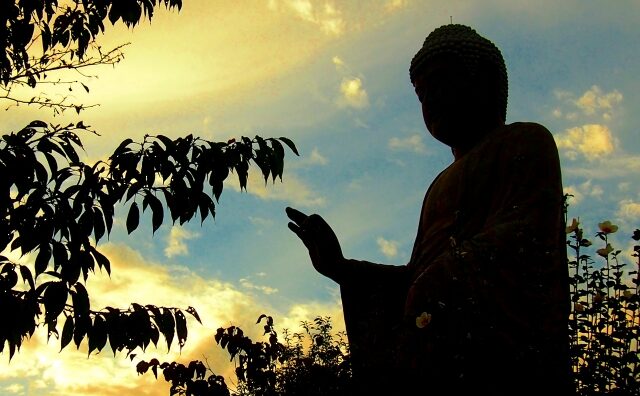 神道・神仏習合
神道・神仏習合 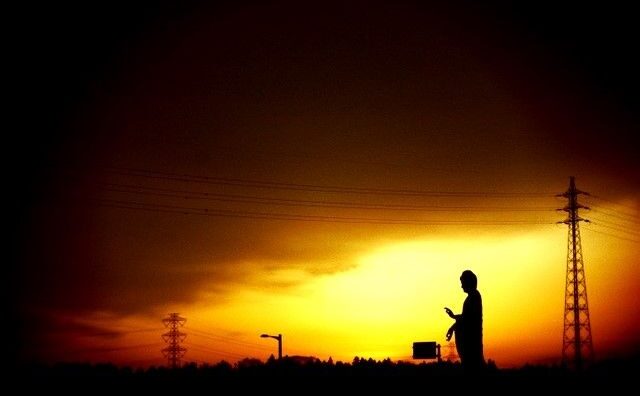 神道・神仏習合
神道・神仏習合