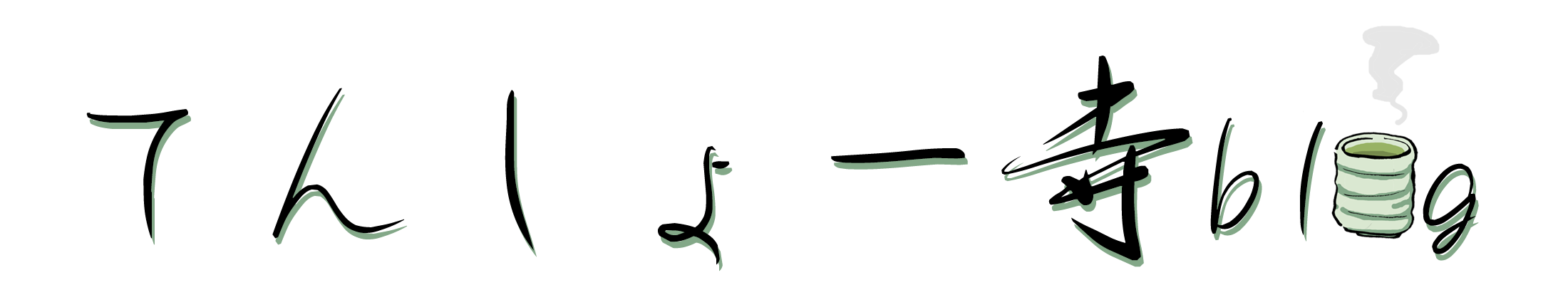ちくちくという痛みで、目が覚めた。
椰子の間から、真夏の太陽がひどく擦りむけた足を照りつけていた。
強い鎮痛剤で朦朧としたまま、しばらく傷を眺めていた。
すると、午前中の出来事が、うっすらと思い起こされてきた。
私たちは、パンガン島の砂だらけの道をバイクで走っていた。
砂でハンドルを取られるたびに、後ろに乗っている友人は豪快に笑いとばしていた。
カーブのたびにスリップしたが、「マイペンライ(大丈夫)」を連呼する友人の勢いにおされ、そのまま運転を続けてしまった。
下り坂にさしかかったとき、ハンドルを砂に取られ横転した。
私の足は、友人とバイクの下敷きになり、そのままの体勢で坂の下まで、ずりずりーっ、とずり落ちていった。
バイクはプラスチックの部分が割れただけだったが、私の右足はかなり擦り減って骨まで削れていた。
光を浴びて虹のように輝く、でっぷりとした銀蠅が、まだ乾燥していない傷口をなめているが、痛みは蠅によるものではなかった。
病院では、骨が見えてるところは包帯を巻いてくれたが、それ以外のかなり深い傷でも消毒しただけだった。
しばらく傷を眺めていると、ちくちくの原因を見つけた。メルヘンの世界にしかいないようなアゴが異常に大きな蟻が、ささくれだった皮膚に噛みついていたのだ。
蟻は固く乾燥した皮膚を噛みちぎろうとして、ユーモラスに首を振っている。
首を振る蟻の向こうには、水色の空と碧く静かな海が広がっていた。
微かな波の音。
椰子の葉が擦れ合う音。
蠅の羽音。
しばらく、蟻の仕事を眺めていたが、蟻はいつまでたっても首を振っているだけだった。
私は、皮膚の乾燥した部分をちぎり取り、蟻に渡した。
自分の身体の三倍はある巨大な食べ物を、蟻は後ろ向けになって引きずって行った。
傷口にたかっている蠅は、六匹だった。
五匹の黒い蠅と、一匹の太った銀蠅。
黒い蠅が傷口にとまっても、さりげないものだったが、銀蠅のそれは、響くような重量感があった。
傷口の上で留まっている間、銀蠅は乾いていないリンパ液の中に口を付けじっとしていた。
ひんやりとした感触が、音律的に伝わってくる。
蠅は、唾液を吐き出して食物を溶かし、それをまた吸い取ることにより、栄養を補給しているのだ。
銀蠅は、手をこすり、頭をくりくり動かして、飛び上がった。そして、すぐまた傷の上にとまって、同じことを繰り返している。
何度も同じことを繰り返した後、銀蠅は尻をもこもこと傷口に伸ばした。
そして飛び上がった。
そこにはなんと、小さな蛆が身をくねらせていたのだ。
卵から生じる蛆しか知らなかったので、いきなり母から生まれ出た新しい生命に、ささやかな驚きと大きな喜びが生じた。
いつの間にか、碧かった海が、沈みゆく太陽に紅く染められていた。
世界は、高度に調和された完全なる美だ。
喧噪の中にあっては、寂静なる世界の真実を認識することはできない。
外的に喧噪を離れ、内的に喧噪を離れ、あの寂静なる場へ赴かなければならない。
知識により加工された認識対象から離れたとき、世界の完全なる美しさを知る。