 真言宗
真言宗 『天地麗気記』書き下し文+現代語訳+解説 まとめ
題名【書き下し文】天地麗気記(かみつかたしもつかたうるはしきいきとうりをきす)この巻の題名です。近世の版本などでは、本巻を巻首に置いているので、『天地麗気記』を麗気記全体の総題とすることもあります。神代七代・過去七仏・北斗七星【書き下し文】...
 真言宗
真言宗  大和葛城宝山記
大和葛城宝山記  中臣祓訓解
中臣祓訓解  中臣祓訓解
中臣祓訓解  中臣祓訓解
中臣祓訓解  中臣祓訓解
中臣祓訓解  中臣祓訓解
中臣祓訓解  中臣祓訓解
中臣祓訓解  中臣祓
中臣祓  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  大和葛城宝山記
大和葛城宝山記  大和葛城宝山記
大和葛城宝山記  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合  神道・神仏習合
神道・神仏習合 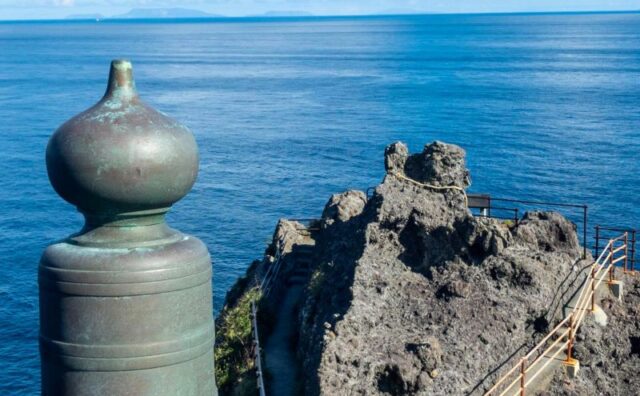 神仏
神仏