 仏教・瞑想
仏教・瞑想 敦煌菩薩と『鹿母経』 竺法護『盂蘭盆経』
盂蘭盆会(うらぼんえ)の典拠(てんきょ)とされる『盂蘭盆経(うらぼんきょう)』は敦煌菩薩(とんこうぼさつ)とも月氏菩薩(げっしぼさつ)とも尊称(そんしょう)された竺法護(じくほうご 239年 - 316年)の訳です。敦煌は地名、月氏は敦煌を...
 仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  常用経典
常用経典  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想 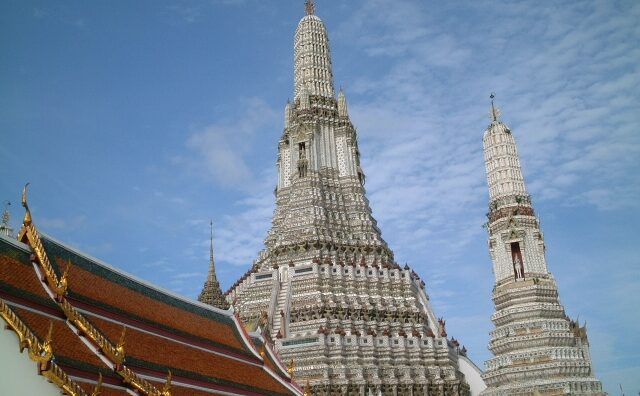 仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  天照寺の行事
天照寺の行事  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想  仏教・瞑想
仏教・瞑想